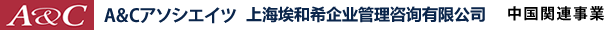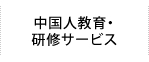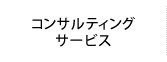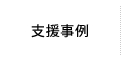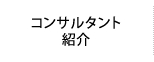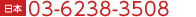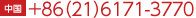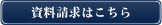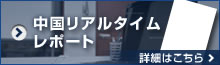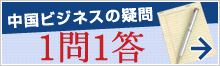中国ビジネス "法務"の1問1答Q&A
中国で個人情報保護法が施行されたと聞きました。どのような点に注意すべきでしょうか。
ここ数年、中国では個人情報保護に関する法整備が進んでいます。
実務においては、顧客および自社従業員からの個人情報を取得する際には同意が必要です。また権限を与えられた者のみが個人情報のリストにアクセスできるようにすることが望ましいです。
個人情報保護に関する法律として、まず2017年には『サイバーセキュリティ法』が施行されました。本法の適用対象はIT企業だけでなく、メーカーや小売事業者までも含まれ、第44条では以下のように定められています。
「いかなる個人及び組織も、個人情報を窃取するか、その他の不法な方式により、これを取得してはならず、個人情報を不法に販売するか、他人に対し不法に提供してはならない。」
また、2021年には『個人情報保護法』が施行されました。違反した事業者には、情状が重い場合は違法所得の没収と5,000万元以下または前年度売上5%以下の罰金、営業許可の取り消しが課される可能性があり、非常に重い罰則が定められています。
なお、中国法人が収集した個人情報を、日本本社が管理する際にも注意が必要です。
詳細については、一度お問い合わせください。
中国では、セクシャルハラスメントとパワーハラスメントについてどのように規定されているのでしょうか。
2021年に施行された『民法典』では、セクシャルハラスメント行為に関する法的定義が盛り込まれました。中国でのセクシャルハラスメントに対する関心の高まりが現れています。
セクシャルハラスメントは、女性に対するものは旧法でも禁止されていましたが、『民法典』では男女問わず禁止されています。また身体的行為以外にも言語、文字、画像などによるセクシャルハラスメントも禁止されました。更に、企業や学校などの組織が、セクシャルハラスメントを防止するための措置を講じる義務が定められているのが、大きな追加です。
一方、パワーハラスメントに関する法的定義は、2022年8月時点ではまだありません。ただし2021年に、とある市のトップが部下に対する暴言や暴力により告発され、解任される事件が起きました。この事件は国営メディアも強く批判をしたことから注目を集めました。パワーハラスメントに対する関心が高まっている事が伺えます。
弊社では、各種ハラスメントを予防するための研修なども実施しています。よろしければお問い合わせください。
自社ホームページ内のみで商品の宣伝を行う場合、広告法による規制は受けないのでしょうか。
自社ホームページにおいても、商品の宣伝を行う場合は広告法の規制を受けます。
そのため、禁止用語を使用していないか、虚偽の説明をしていないかなど、精査した上で掲示することが必要です。
広告法に抵触する表現を教えてください。
「中華人民共和国の国旗などを使用する」「社会公共の秩序を妨害する」などいくつかありますが、特に注意が必要なのは「国家級、最高級、最良等の用語を使用する」ことです。「等」とあるように解釈の幅が広く、例として挙げられている3つの用語以外に、どのような表現に注意すべきかは広告法内で明示されていません。しかしながら実際には「最大」「NO.1」「トップレベル」などの用語も対象となります。
具体的にはよろしければお問い合わせください。
中国では、広告上の表現が厳しく規制されていると聞きました。実情はどうなのでしょうか?
中国における広告に関する法規制として、『広告法』があります。本法は2015年に修訂され、非常に厳格であることが知られています。
抵触した場合には20万元から100万元の高額な過料が定められており、場合によっては、営業許可証が取り下げられる可能性もあります。
最近では消費者の目が厳しくなっているのはもちろんですが、報奨金目的に告発するケースが少なくありません。
広告を出す際には、禁止用語を使用していないかしっかりと確認することが必要です。
中国事業の撤退を考えています。どのような方法がありますか?
事業撤退の方法には、以下三種類があります。
1)持分譲渡 2)清算 3)破産(倒産)
いずれの場合も、「出資者全員の合意」「董事会での全会一致」「審査認可機関の許可」が必要です。
どの方法を選ぶのが良いのかは、会社資産や従業員との関係など状況を総合的に検討した上で判断しなければなりません。
中国の弁護士事務所や会計事務所などに直接相談すると、清算手続き業務を受託するために事業撤退を強く勧められることが多いようです。
しかし、撤退以外にも、新たなパートナーを見つけたりするなど、再建して事業継続する方法もあります。
特に2020年3月時点では、新型コロナウイルス関連に伴い、都市によっては法人への何種類かの優遇処置もあります。
冷静かつ総合的にご検討ください。(2020年3月)
中国事業の撤退時の注意点があれば教えてください。
特に注意が必要なのは、以下三つの相手です。
1)従業員
「経済補償金」を支払わなければなりません。基本的には、勤務年数1年間につき1ヶ月分給与の相当額を支払うことになります。法定の最低限で合意が得られない場合もあるので、事前に慎重な対応が必要です。
また、組合に相当する「工会」がある場合、合意も必要となります。
2)現地政府
現地商務部門の許認可に加え、工商、税務、税関、外貨、統計、財政、社会保険などさまざまな抹消手続きが必要です。現地政府にとって企業撤退は、税収入減となるため円滑に進まないこともあるので、慎重に十分な準備が必要です。
また、経済特区など進出時に優遇を受けた企業や、税務上コンプライアンス違反を隠している企業は、手続きが一層困難になるため、詳しい弁護士に相談してください。
3)事業パートナー
日本本社独資の場合はさほど問題になりませんが、中国側パートナーとの合弁会社の場合には、自らの出資分だけでも取り戻そうとすることもあるため、トラブルになることもあります。清算手続きには「董事会の全会一致」が不可欠なため、中国側パートナーの協力が得られない場合、手続きさえ開始できないということもあります。
また、法人清算後、中国側パートナーが会社の特許情報やクライアントの機密情報を持ち出し、競合会社に販売するという事案もあるので、注意が必要です。(2020年3月)
中国において、契約内に明示されていない事項は、どのような解釈が取られますか。
例えば、A社がB社と商品購入の契約を締結しようとします。A社はB社の製造工場を見学した上で、購入商品の規格、数量、金額、納期について双方合意し、契約を締結しました。
しかし、B社は生産能力が足りず、契約規定に合致する商品を他社から調達し、A社に納品しようとしました。A社はこの状況を知り、商品がB社製品ではない事を理由に、契約履行を拒否しました。
B社は、契約に商品製造者についての制限を明記していない事と、納品する商品が契約の規定に合致する事から、A社の履行拒否は違約責任が生じると主張しました。
裁判所の判決では、A社はB社工場を見学した上で契約を締結した事から、製品はB社製造のものであると黙示に合意したとされました。A社の認識が取引習慣と認められ、B社の主張は却下されました。
■背景:
中国「合同法」に基づき、契約内に明示されていない事項に対し、当事者間で補充契約の合意に達せない場合、取引習慣を参照するとされています。
中国において、公平性を欠く契約は解除できますか。
取消できる可能性があります。
例えば、A社が顧客と商品販売の契約を締結したとします。契約には、1ヶ月後に納品しない場合は高額な違約金が課されると明記されています。出荷日が迫りましたが、A社は台風の被害により、倉庫の原材料が水没してしまいました。生産を再開するため、B社からその原材料を急遽仕入れしようとしました。
するとB社はA社の状況を知り、通常より5倍の金額で請求しました。A社はやむを得ずB社の見積もりを受け取りました。
B社と契約を締結した3日後、A社は別のサプライヤーから同じ原材料を調達できたため、B社との契約を取消したいと主張しました。
しかしB社はA社の要求を受け入れず、約束の金額で契約を履行させようとしました。
裁判所の判決により、B社がA社は高額の違約金を課されることを知り、不合理な価格で契約を結んだ場合、A社の主張通り契約取消が認められます。
■背景:
中国「合同法」に基づき、当事者の弱みに付け込んで締結された契約と、公平性を欠く契約は、取消の求めを認めることができます。
中国において、契約相手の履行不能が予期され、かつ契約が解除できない場合の救済手段はありますか。
あります。
例えば、A社がB社から商品を特注する契約を締結したとします。契約にはB社が規定日までにA社指定の品物を加工し、A社が約束の出荷予定日の1週間前に商品代金を支払うと明記されています。
契約規定の支払日に至り、A社は請求書を受け取りました。しかしB社は自社責任により、消防局に生産停止を命じられ、再開予定が暫く見通せなく、契約規定の納品日に間に合わないとしました。
この際、A社からの一方的な契約解除の主張が裁判所に認められず、且つ契約相手が履行不能と予期された場合、A社は自社の権利を救済するため、先行義務である商品代金を支払うことについて「不安の抗弁権」を主張することができます。
■背景:
中国「合同法」に基づき、先に履行すべき当事者は、契約相手方に契約履行不能の事由が存在することを証明できる場合、履行を中止できます。ただし、相手方が適当な担保を提供することなどにより、合理的期間内の履行能力を証明できた場合、履行すべきと明記されています。
- 本質問のお問い合わせはこちら
- 本質問に関するWebからのご質問・お問い合わせはこちらから。
- お電話の場合は、下記にお問い合わせください。
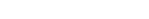
A&Cアソシエイツ株式会社
03-6238-3508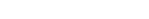
上海埃和希企业管理咨询有限公司
+86(21)6171-3770 日本語、中国語可